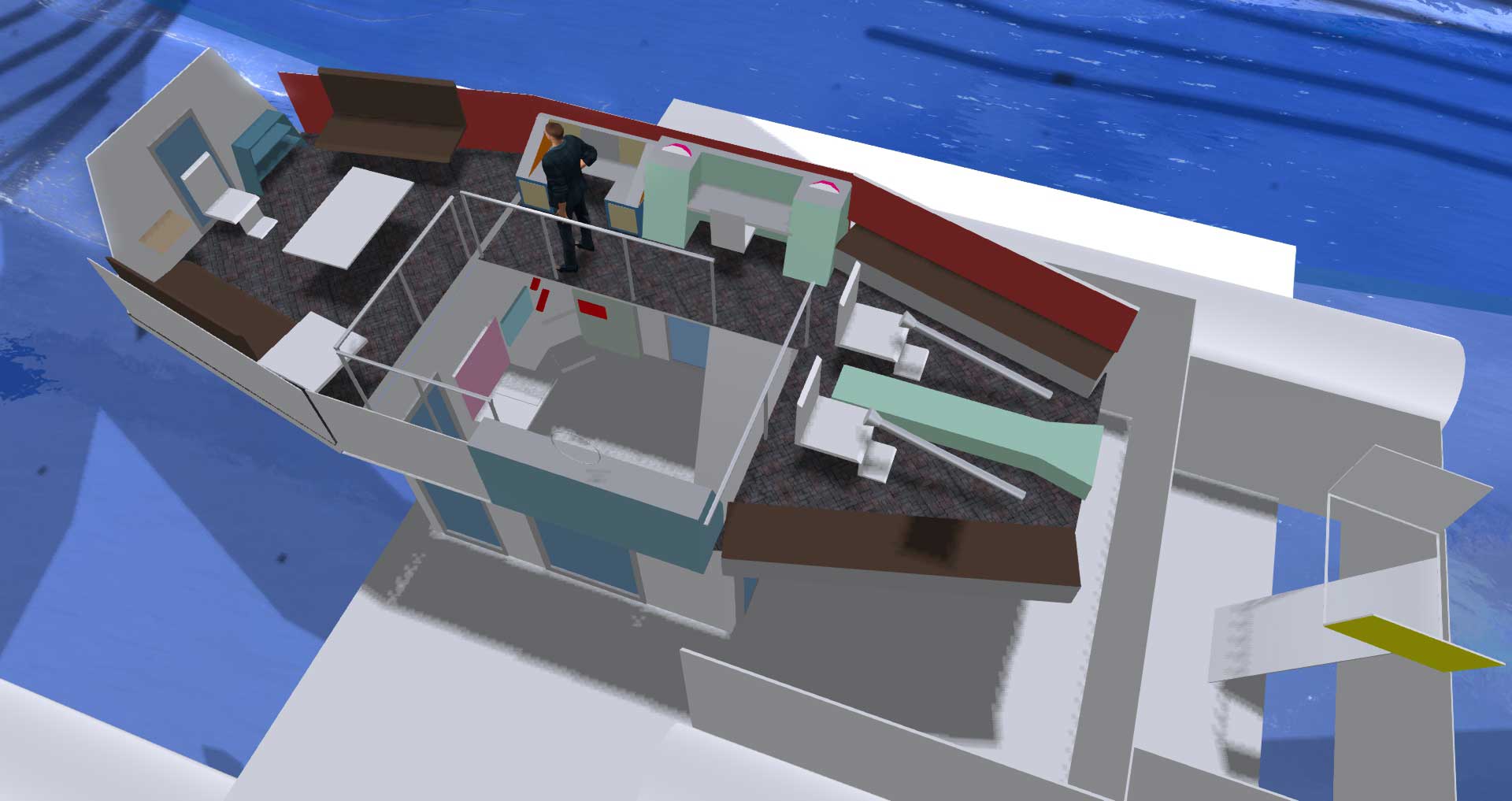別に教育利用に限った話ではないのですが、SLやOpenSim(あわせてVW)のビュワー映像をウェブ会議システムで他の参加者に見せる方法です。
Skypeは事前に参加者全員との間でやらなければならない準備が大変なのに比べ、ZoomはミーティングURLを通知すれば、あとは参加者側でなんとかしてくれるので、初めての参加者が多い見学会などには好都合です。Webexも同様ですが、Webexアカウントを作ってから1か月を過ぎるとミーティングの時間に関わらず有料になってしまいます。
ところが、Zoomの画面共有でVWビュワー映像を他の参加者に見てもらうと、フレームレートがめちゃめちゃ落ちてしまいます。これは自分自身では分からないので、他の参加者に録画してもらって見せてもらいましょう。ガッカリします。SkypeとWebexでは動画の共有に最適化するオプションがあるので、それでZoomも大丈夫だと思ってたらとんでもないです。
方法ですが、Zoomのウェブカメラ映像のフレームレートは画面共有よりもずっと高いです。そこで、「仮想ウェブカメラ」というものを使って、VWビュワー映像をウェブカメラ映像として入力します。自分の顔を写すためのウェブカメラを三脚に載せてPCモニターを写してもいいですが、モニターの前に座っている自分が邪魔。
また、VWツアー参加者はシェアされた画面を見てるだけじゃなく、自分でSL内を移動していかなければならないので、もしZoomが全画面表示だったらそれを解除するとかタスクスワップするとかが必要。
⑩ バーチャル見学会ではVW内で聞こえる様々な音も重要な要素の一つ。参加者がみんな自分のVWビュワーを立ち上げてれば大丈夫だが、そうでない人もいる場合はVW内の音もZoomにインプットしたいところ。ところが仮想ウェブカメラはVW内の音まではZoom入力しないので、Zoomの「画面共有」で「コンピュータサウンドのみ」を選択すればいいだけ。VWビュワーを画面共有しないんだから「画面共有」は一切関係ないと思ってしまうところですがご注意。